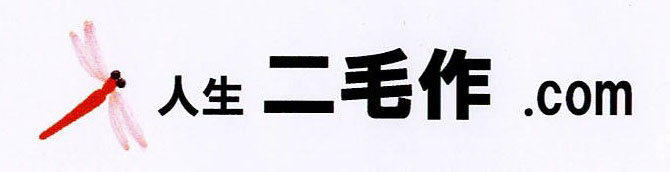「漱石詩注」序(吉川幸次郎)
「漱石詩注」序(吉川幸次郎)
【序】に・・・
(この素人の漢詩)漱石の詩が、日本人の作った漢語の詩として、すぐれることである。もう一歩を進めて言うならば、日本人の漢語の詩として、めずらしくすぐれることである。
原因は、“思索者”の詩である点で、おおむねの日本人の漢詩と異なる、ということにある。
先生の漢語は、その語法についていえば、きわめて正確である。いわゆる日本漢文、日本漢詩では、断じてない。のちに述べるように、中国人で先生の詩を激賞するものがあるのは、何よりもそれを物語る。
~ また漢詩の成立にはほとんど不可欠の要素である典故、classical allusion その使用も、非専門家の限界を超えない。それらの点で、結局は素人の漢詩であるという要素を持つ。
しかしこの素人の漢詩は、二つの点で重要である。一つは、いうまでもなく、先生の文学の一部分としてである。単に余技としての遊戯の作を、全然含まないというのではない。~ 第二は、その詩が、日本人の作った漢語の詩として、すぐれていることである。もう一歩を進めて言うならば、日本人の漢語の詩として、めずらしくすぐれていることである。その原因は、思索者の詩である点で、おおむねの日本人の漢詩とことなる、ということにある。
詩は直感の言語である、という定義があるとするならば、恐らくそれは正しい。しかし漢語の詩に関する限り、思索を排除した直観のみでは、充実した詩を得難い。事がらはおそらく、漢語の本来持つ性質と、関係している。漢語は、簡潔、ということが、その性質の一つであると普通言われるように、飛躍の多い直観的言語で、そもそもある。詩の言語となる漢語は、ことにそうである。
ということは、それだけに、簡潔の裏に、あるいは簡潔の前提として、思索の熟慮を蔵しなければ、飛躍とならない、ということである。むろん詩としてまず必要なのは、一読して、飛躍の爽快さを感ずることである。しかし再読して、飛躍の前提となった熟慮を追跡し得るものでなければ、良い詩にはならない。
☞ 意味がよく理解しにくい! 素愚
漢語の詩の本家である中国の詩は、常にこの方向にある。必ずしも大家の詩ばかりではない。そのおおむねがそうである。
単に「風雲月露」の美しさを、感覚的にとらえ、詠嘆するだけではいけない。花が散る、日が落ちる、そこに人間の運命なり使命への関心が、反映しなければならない。
もしそうでなければ、飛躍と見えるものは、単なる粗笨な豪語、あるいは軽佻浮薄な機智となって、空虚な音声をつらねるにすぎない。 (p11)
幸か不幸か、日本文学の本来もつ伝統は、こうした漢語の詩の要求する方向と必ずしも一致しない。
詩はいかなる意味においても思索を忌避する、そうした方向が、日本の詩の伝統として有力である。
明治41年の講演「創作家の態度」で、漱石がした規定を借りれば、「科学的精神」が欠乏し「芸術的精神」がありあまる過去の日本文学は、「情操文学」が過半であり、またその系統のものが優(すぐ)れる。けだし「古今和歌集」は、いわゆる「優れる」ものの代表であろう。しかしこのことは、すぐれた漢語の詩を容易に生み得べき方向性ではない。
この矛盾が、古今往来、日本人の漢詩を、ちぐはぐな、面白くないものとしてきたと、見うけられる。「懐風藻」をはじめ、奈良平安朝人の漢詩は、もともとそうである。更にまた江戸時代は、漢詩の最盛期の一つであり、当時の漢詩の作者は、儒者であった。儒者は思索者であるが、儒者も詩を作るときは、別の態度に立つ。故にその時は、依然として面白くない。たとえば徂徠は、もっとも思索者であり、その漢文は前にふれたように、先生の愛賞にたえた。しかしその漢詩は、面白くない。
もし過去の日本人の漢詩のうち、やや例外となるものを求めれば、足利時代、五山の僧徒の詩であろう。義堂周信、絶海中津はともに五山文学の秀才であり、やがて絶海中津の「蕉堅稿」は、先生の愛読書となって、「机上の蕉堅稿」の句を生む (p175)。
またもし江戸時代における例外を求めるならば、先生の書法に影響を与えたとおぼしい良寛上人の詩が、その一つかと、思われる。 (p12)
そうした日本文学の情勢の中で、あるいは更に強めていえば、そうした歴史の中で、先生の漢詩は、例外的に“思索者の詩”である。つまり先生の漢詩は、局部的に職業詩人に比して素人であったけれども、もっとも大きな点では、かえってくろうとであった。
先生自身が、俳句よりも漢詩を愛重したのも、後者の方が、その“思索を託する”のに、より適すると感じたことが、有力な原因の一つとして働いていよう。 (p13)
「風流」とは何か。西洋には「見当らぬ」といえば、西洋的な文学とは、対蹠的なものである。少なくとも対蹠的な要素を持つものである。そのやや前、明治40年になされた講演「文芸の哲学的基礎」で、「天地の景物を詠ずる事を好む支那詩人もしくは日本の俳句家」といっているのを思いあわせれば、人事の葛藤に関する西洋的文学、その対蹠として、柔順な自然、柔順なゆえに清潔な自然、それに感心すること、あるいはその中に没入すること、それが「風流」であるように思われる。
それは思索を拒否する態度ではない。自然への没入、それがすでに一つの思索である。しかしその際に、貴ばれる思索は、人事の葛藤に関心する際の如き複雑な思索ではない。単純ではなくとも、純一な思索である。 (p14)